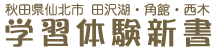歴史と伝統学習 - 日本独自の学問再発見
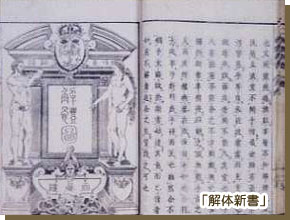 角館は「文教の地」とも言われています。藩政時代の前半、言葉では「文武両道」とは言ったものの必ずしも学問が好まれたわけではありませんでした。その中で「致道館」「弘道書院」などの武士の学校が開かれ、この地に学問の花が開花しました。
角館は「文教の地」とも言われています。藩政時代の前半、言葉では「文武両道」とは言ったものの必ずしも学問が好まれたわけではありませんでした。その中で「致道館」「弘道書院」などの武士の学校が開かれ、この地に学問の花が開花しました。歴史的にも貴重なものとして、日本独自の数学「和算」の上達を祈願した「算額」が現存しており、また、角館の武士「小田野直武(おだのなおたけ)」が挿し絵を描いた「解体新書」も完全な形で見ることができます。
今につながる学問の一端に触れてください。
「解体新書」を描いた絵師
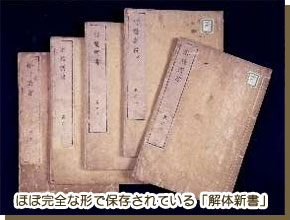 日本初の西洋解剖学書「解体新書」(ターヘルアナトミア)。その精巧な挿し絵を描いたのは角館の武士「小田野直武」でした。
日本初の西洋解剖学書「解体新書」(ターヘルアナトミア)。その精巧な挿し絵を描いたのは角館の武士「小田野直武」でした。当時、鉱山開発のために久保田藩に招かれた平賀源内から西洋画の技法を学んだ直武は、これまで平面的だった日本画に西洋美術の3次元的な表現を取り入れ、日本における西洋画の先駆けとなった「秋田蘭画」という独自の画風を生み出しました。
角館には「解体新書」が何冊か遺されており、その中の一組はほぼ完全な形で保管されています。
近代美術と小田野直武
直武は解体新書の絵師というよりも、実は我が国の近代美術の中で重要な位置を占めています。東京国立近代美術館のギャラリーガイド「近代日本美術の名作」のはじめ書きの中で本江邦夫氏が次のように書いています。「日本の美術が、こうした近代的意味での写実性を獲得したのは(あるいは獲得するのは)いつのことか断定するのはむずかしい。はっきりしているのは、ともかく江戸後期、蘭学の流行もあって西洋美術の線遠近法などの3次元的な表現が高まり、それが結果として旧来のあまりに平面的で装飾的な日本絵画にたいする批判的な視点を生み出したということだ。小田野直武を中心とする秋田蘭画はその典型といえよう。」
はじめ書きの中で一番最初に出てくる画家の名前が直武です。
様々な評価があるにしても、直武は司馬江漢へとつながる日本の近代美術の礎となった先駆者であることに間違いありません。